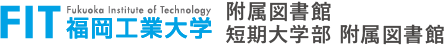日本学術会議 学術フォーラム「ケアの多様性・包摂性・公平性・持続可能性」
| 講座名 | 学術フォーラム「ケアの多様性・包摂性・公平性・持続可能性」 |
|---|---|
| 開催日・時間 |
2025年12月21日(日)13:00~16:00 |
| 対象 | どなたでも参加いただけます・無料 |
| 会場 | 日本学術会議講堂(東京都港区六本木7-22-34) オンライン配信あり 手話通訳・文字通訳付 |
| 開催趣旨 |
連続シンポジウム及び学術フォーラムにより、人間にとってケアをする/されることの意味やケアの双方向性・重層性など多方面からの考察を行い、ケアサイエンスという新しい学問的見地から、直面している問題の核心を探る。そして、関連する学問分野や実践活動の担い手、制度の担い手など多様な関連主体がより効果的に連携・協働できる提案や見解を見出すことを目的とする。 |
| プログラム |
コーディネーター:熊谷晋一郎(日本学術会議第二部会員、東京大学先端科学技術研究センター当事者研究分野教授) 13:55~14:25 第二部 ケアへのアクセシビリティの格差 |
| 申込URL(オンライン) | 学術フォーラム「ケアの多様性・包摂性・公平性・持続可能性」 |
日本学術会議 公開シンポジウム「分断化する社会の中で対話は可能か――ポスト・ソーシャルメディア時代の社会構築」
| 講座名 | 公開シンポジウム「分断化する社会の中で対話は可能か――ポスト・ソーシャルメディア時代の社会構築」 |
|---|---|
| 開催日・時間 |
2025年12月21日(日)13:00-17:00 |
| 対象 | どなたでも参加いただけます・無料・要事前申込 |
| 会場 | 立教大学池袋キャンパス11号館AB01教室(ハイブリッド開催) |
| 開催趣旨 |
今日の社会における利害や意見の対立は、共存や相互承認に至ることなく、激しい分断へと導かれている。この分断は、コロナ禍によって対面交流が制限されるなか、ソーシャルメディアによって加速している。ソーシャルメディアや動画共有サイトの発達は、人々の情報共有を容易にしたが、考えが異なる者を敵とみなし攻撃することも日常化してしまった。 |
| プログラム |
司会(第一部):吉水 千鶴子(日本学術会議第一部会員/筑波大学人文社会系名誉教授/公益財団法人東洋文庫研究部研究員/日本宗教研究諸学会連合副委員長) 第二部 哲学カフェ――第一部講演をテーマとして |
| 申込URL(オンライン) | 公開シンポジウム「分断化する社会の中で対話は可能か――ポスト・ソーシャルメディア時代の社会構築」 |
AJACS「空間トランスクリプトーム解析を知って・学んで・使う」
| 講座名 | AJACS「空間トランスクリプトーム解析を知って・学んで・使う」 |
|---|---|
| 開催日・時間 |
2025年12月18日 (木) 13:30-15:50 |
| 会場 | Zoomウェビナーによるライブ配信 (予定) ※ 詳細は、ご登録いただいたメールアドレスへ開催日の数日前までにご連絡いたします。 ※ 受講に必要な端末・回線等はご自身でご準備ください。 ※ 受講者の環境・設定等によって受講できない場合の対応はいたしかねます。 |
| プログラム |
13:30~13:40 NBDCの紹介 まず、Rを用いた空間トランスクリプトミクス解析の基礎から応用までを紹介します。 15:10~15:50 解析事例(腫瘍微小環境/SKNY) 酒井 俊輔氏 (東京大学) |
| 主催 | 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) |
| 共催 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 データサイエンス共同利用基盤施設 ライフサイエンス統合データベースセンター(DBCLS) |
| 申込 | AJACS「空間トランスクリプトーム解析を知って・学んで・使う」 |
AJACS「日本人ゲノムバリアント解析ツールを知って・学んで・使う」
| 講座名 | AJACS「日本人ゲノムバリアント解析ツールを知って・学んで・使う」 |
|---|---|
| 開催日・時間 |
2026年01月22日 (木) 13:30-15:50 |
| 会場 | Zoomウェビナーによるライブ配信 (予定) ※ 詳細は、ご登録いただいたメールアドレスへ開催日の数日前までにご連絡いたします。 ※ 受講に必要な端末・回線等はご自身でご準備ください。 ※ 受講者の環境・設定等によって受講できない場合の対応はいたしかねます。 |
| プログラム |
13:30~13:40 NBDCの紹介 14:50~15:50 TogoVar の活用事例で学ぶバリアント 三橋 信孝氏 (DBCLS) |
| 主催 | 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) |
| 共催 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 データサイエンス共同利用基盤施設 ライフサイエンス統合データベースセンター(DBCLS) |
| 申込 | AJACS「日本人ゲノムバリアント解析ツールを知って・学んで・使う」 |
もっと知りたい!JDreamⅢ実践セミナー
| 講座名 | もっと知りたい!JDreamⅢ実践セミナー |
|---|---|
| 開催日・時間 |
2025年12月17日(水)14:00-15:00 |
| 会場 | オンライン(zoom) |
| 概要・コンテンツ |
JDreamⅢをすでにご利用いただいている皆様に向けて、複数条件の組み合わせや細かい条件指定が可能な「アドバンスドサーチ」を中心に応用的な使い方をご紹介します。 ・基本的な使い方の復習 |
| 対象 | JDreamⅢをすでにご利用いただいている方 検索精度を高くしたい方、頻度分析や、可視化などの機能をつかいこなしたい方 |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 25名 |
| 申込URL | もっと知りたい!JDreamⅢ実践セミナー(12/17) |